一流音楽プロデューサー、思いのままにサウンドをあやつり、タッチする楽曲をヒット曲へと変貌させる存在です。彼らは一体何を考えて日々のスタジオワークに臨んでいるのでしょうか?
サウンドに対する技術的なこだわりは当然して、キャリア・お金・仕事仲間とのスタンス、仕事に関する哲学など、彼らがどういった視点を持っているかは興味深いテーマと言えるでしょう。
ここでは私が海外の一流音楽プロデューサーの方数人(ゴールド含む)から、直接間接的に伝え聞いて、得心した部分のみをピックアップしてご紹介します。
海外ということで日本とやや事情が異なる面がありますが、我々の日常の業務でも生かせる学びがきっとあるはずです。
この記事は
- 一流の海外音楽プロデューサーが何を考えているか知りたい
- 結果を叩き出す人間のマインドを知りたい
- “プロ意識”を垣間見てみたい
といった方におススメです。

① 未完成・低品質の作品は公開してはならない
この言葉の真意は、クオリティの低い作品の露出は自身のブランド価値を下げるので、作品を外部に公表する際には慎重であれ、ということです。
趣味で音楽を作っている場合はまだしも、プロを指向するのであれば、自作の音源の品質を顧みず、周囲にばらまく行為はややリスキーかもしれません。
他に、以下のような理由も考えられます。
- 客観的視点が無いと思われる
- スキルが低いと思われる
- プロ意識が低いと思われる
ちなみに自分の作品のことを試作品と呼ぶ方がたまにいます。しかし呼び名こそ試作品でもクオリティは完成品にまで高めておくべきかと思います。
「自分はまだヒヨッコだからお試しレベルで大目に見てほしい」という発想は甘えで、そのように好意的に受け取る依頼主は多く無いでしょう。公にするなら、スキルが発展途上であってもベストを傾注して“完成”させましょう。
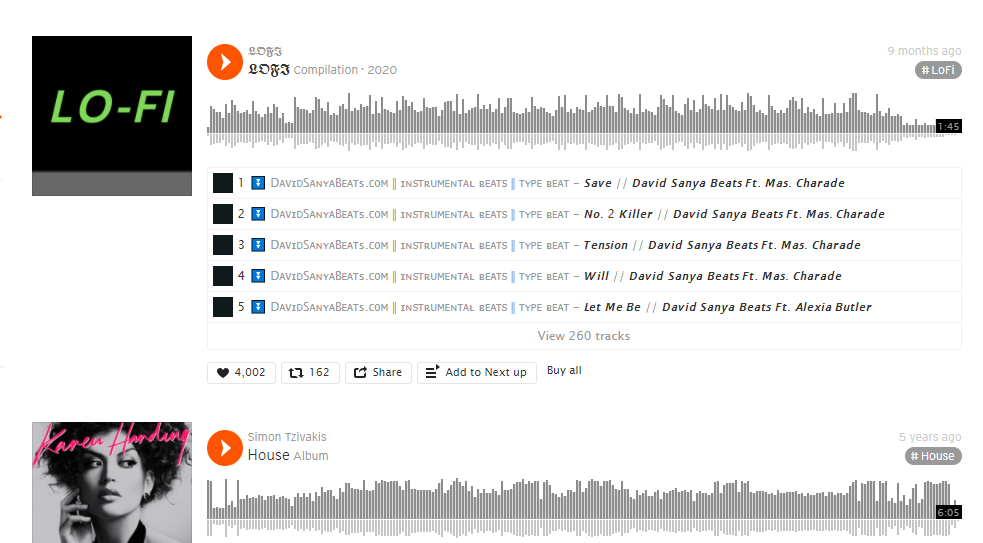
公開する作品のクオリティは出来るだけ高いものを
途中段階の作品を公開する必要は無い
不思議なことに、若くしてこの発想を持っている人もいれば、長いキャリアがあっても無自覚な人もいるようです。この類のプロ意識はキャリアの長さとそこまで相関関係が強くないのが印象的です。

② リリース前に出来ることは全部やる
彼らの一人が語るには、楽曲のリリース後に
「どうしてここを直しておかなかったのか?」
「もっと良いアプローチがあったのでは?」
という不満がつねにあると語ります。一旦リリースしたが最後、その後でどんな手残りが見つかっても修正は一切ききません。
そんな制作スタンスだといつまでたっても完成しないでは無いか、と言われそうですが、おそらくそれを承知の上で、リリース作品はパーフェクトを目指さなくてはならないという意思の表れなのでしょう。
「朝起きたらスタジオに入り、夜意識が飛んで眠りにつくまでサウンドをいじくりまわす。これを何週間もぶっ続けでやる」「ベストフィットのハイハットのサンプルを探すのに5日間かけた」
やや極端な例ですが、これらはスウェーデンのプロデューサーユニット、 Swedish House Mafia のメンツが語った言葉。あちらのトッププロデューサーは完璧を期すために、文字通り命を削って曲を作っているようです。
もちろん仕事には持ち時間があります。なので完璧主義を最後まで貫くのは非現実的。しかしながらその範囲で完璧に近づけるため出来ることは全部やる、そういう彼らの執念は見習いたいものです。

③ 二流のミュージシャン・シンガーとの仕事は時間のムダ
そもそも一流とそれ以外の違いはなんなのか?と問われると明確な線引きは難しいですが、おそらく以下のようなものを一流と考えます。
- パフォーマンスのレベルが高い
- 楽曲に新しい感覚を吹き込んでくれる
- 品質向上に積極的にコミットする姿勢がある
- ポジティブなムードで仕事ができる
こちらの意向を踏まえた上で、楽曲のクオリティをアップさせるためのアイデアを積極的に提案してくれる、そういうミュージシャン・シンガーはとても感謝されるでしょう。なぜならプロデューサーの頭の中には、具体的なサウンドのイメージが常にあるわけでは無いからです。
残念なパターンが
- 指示待ち
- 見当違い
- プロ意識の欠如
「指示待ち」は言われたこと以外やらない人、「見当違い」は曲の方向性あるいは自分の役割を理解していない人。
まれにあるのが「適当にやるんで、あとで良いテイク選んどいて」と言う人。気持ちは分からなくもないですが、ジャッジの丸投げは責任放棄と同じでプロ意識を疑われます。

やはり一流は一流としか仕事をしないことが多い
これの逆が、ジャッジを下す側がOKを出していても、ミスがあればそれを自発的に認め自分からリテイクを申し出る人でしょうか。こういった人からは、自分も制作曲のクオリティの責任の一端を担っているのだ、という気概を感じます。

④ ボーカルが楽曲の主役である
プロデューサーの目的はヒット曲を手掛けお金を稼ぐこと、そしてヒット曲に欠かせない要素がボーカルです。チャート上位を占めるのはほとんどボーカルをフィーチャーした楽曲で、インストゥルメンタルがチャートに上ることは中々ありません。
私が聞いたのが「手持ちの時間の多くをボーカルのポリッシュアップに費やせ」というもの。ボーカルが大切なのは誰でも理解していますが、その徹底した品質管理までには思いが至らないことが多いかと思います。
英語圏以外での仕事の時のこと。ボーカルのエディットや調整時に、現地の人間に言葉の意味や文節に関して、折に触れて何度も確認していたと言います。
母国語でない言語のため、シンガーの声色から細かなニュアンスを感じ取るのが難かしかったからかもしれません。
不自然な言葉の切れ・イントネーションになっていないか、あるいは歌唱内容的にどんな聞かせ方が効果的か、などの判断基準として知りたかったのかもしれません。
いずれにしろ、単なるルーティン作業に留まらない、レコードの細部まで注意を払う彼らのプロ意識を感じるエピソードです。

ボーカルを雑に扱うのは厳禁
なお、一流のプロデューサーはクライアントが大手のレーベル、ないしは有名アーティスト自身であることも多く、制作する楽曲がメジャーなシンガーを顧客としてターゲットに含めているという側面も、彼らがボーカルに執心する理由になっています。
自分の歌声が楽曲中で素晴らしく聞こえるなら、是非このプロデューサーと仕事がしたい、アーティストなら皆そう考えるのが自然でしょう。
彼らは、手掛けるリリース作品を通して世界中のリスナーだけでなく、アーティストにもアプローチしているわけです。

関連記事
本記事に関連する内容の記事です。
- Avicii に学ぶEDMでブレイクする7つの秘訣
- Calvin Harris ヒット曲量産の裏にある隠れた7つのエピソード
- David Guettaから若手EDMプロデューサーへ4つのアドバイス
- The Chainsmokers が贈るスタジオワーク5つの心構え
- NickyRomeroに学ぶ6つのEDMサウンドメイキングの秘訣

まとめ
本当はもっとたくさんの「プロとしての心構え」を学びましたが、私が見聞きして強く印象に残ったのがここでご紹介した4点です。
彼らから機材の使い方など、具体的な手ほどきを受けたことはほとんど無いのですが、一流のプロとしての考え方に大いに感化されたのは覚えています。
若い頃に師事した人間、キャリア序盤に接した先達によってその後の音楽人生が大きく左右されることがあります。感性のみずみずしい若いうちに、こういった一流の人間の思考に触れておくのは有意義では無いでしょうか。
スキル獲得の学習や習練も大切ですが、それと同時に出来る限り一流に近い人物を見極め、近づき、可能であればその仕事の流儀を間近で体感されることを、ぜひお勧めいたします。

